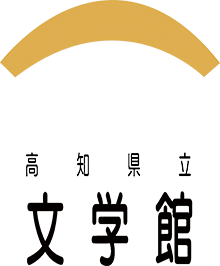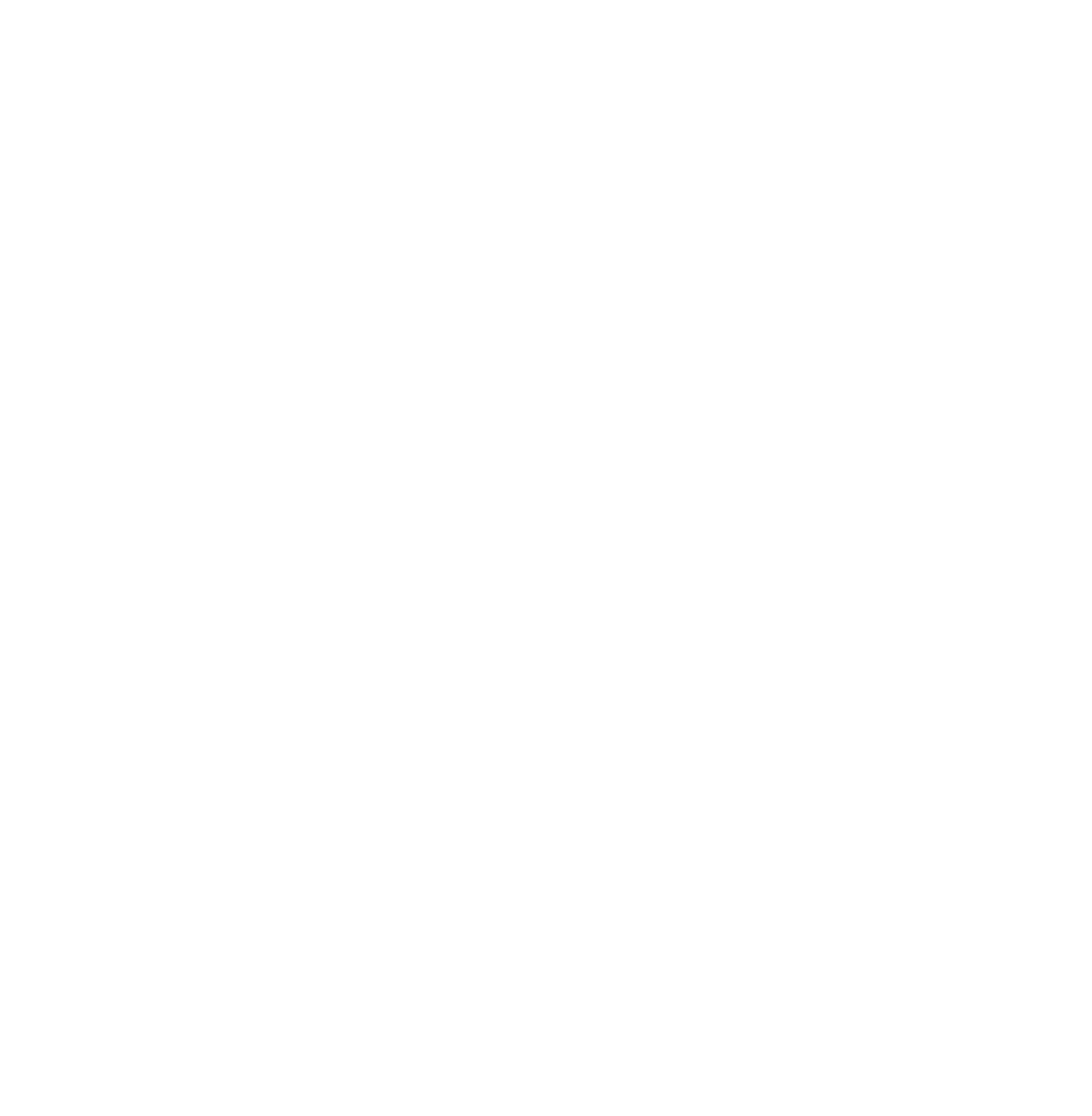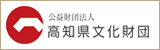東京都生まれ。歌人。短歌を中心に戯曲、小説、随筆、歌謡など多角的な活動で多くの作を残す。私生活の苦悩の末、昭和9年に香美郡猪野々(現・高知県香美市香北町猪野々)に草庵を移築し隠棲の地と定める。土佐は、勇の再生の地であり、
広島県生まれ。作家。小説、随筆、紀行、詩、童話などを温かなユーモアと悲哀を織り交ぜ執筆、翻訳も手掛けた。若き日の文学修行時代の師でもあり仲間でもあった田中貢太郎の病気見舞いなどで幾度となく高知を訪れ、高知を材にした作品も
高岡郡窪川町(現・四万十町)生まれ。作家。詩人としてのみならず、訳詩、評論、史伝など幅広い分野で活躍している。詩集『永久運動』で岡本弥太賞を受賞。<おもな著作>『裏返しの夜空』『詩とは何か』等
大阪市生まれ。名誉高知県人として県民に親しまれている司馬は、高知の人と風土にひかれ、土佐を題材とした多くの作品を書いた。「竜馬がゆく」を頂点とする長編歴史小説や紀行文「土佐の街道」、エッセーなど高知に関する作品は、司馬作
先日、当館に大岡昇平書簡が14通寄贈されました! この書簡は、土佐藩が関わった堺事件を題材とした小説『堺港攘夷始末』を 大岡が執筆する少し前から、高知県の郷土史家とやりとりされたものです。 『堺港攘夷始末』は、森鷗外の小